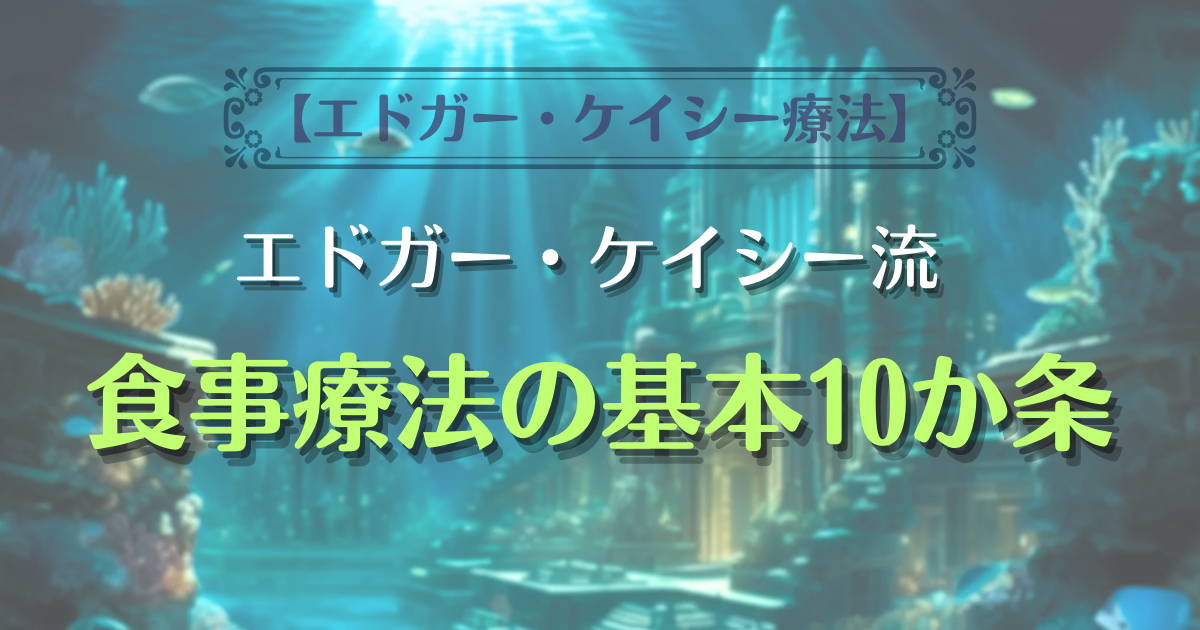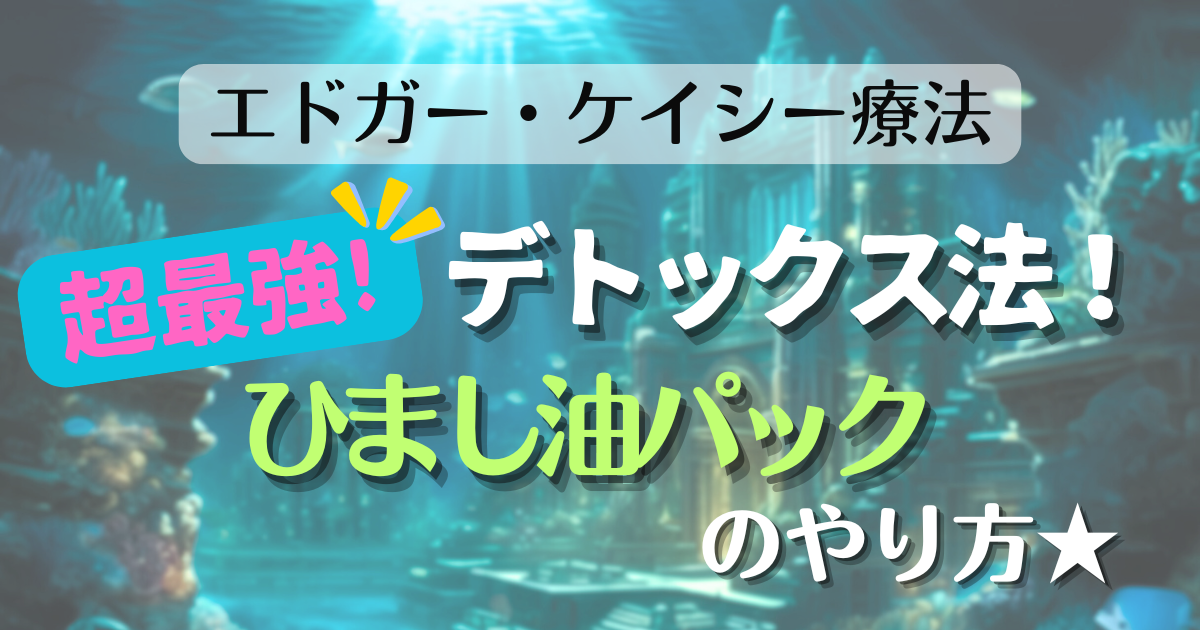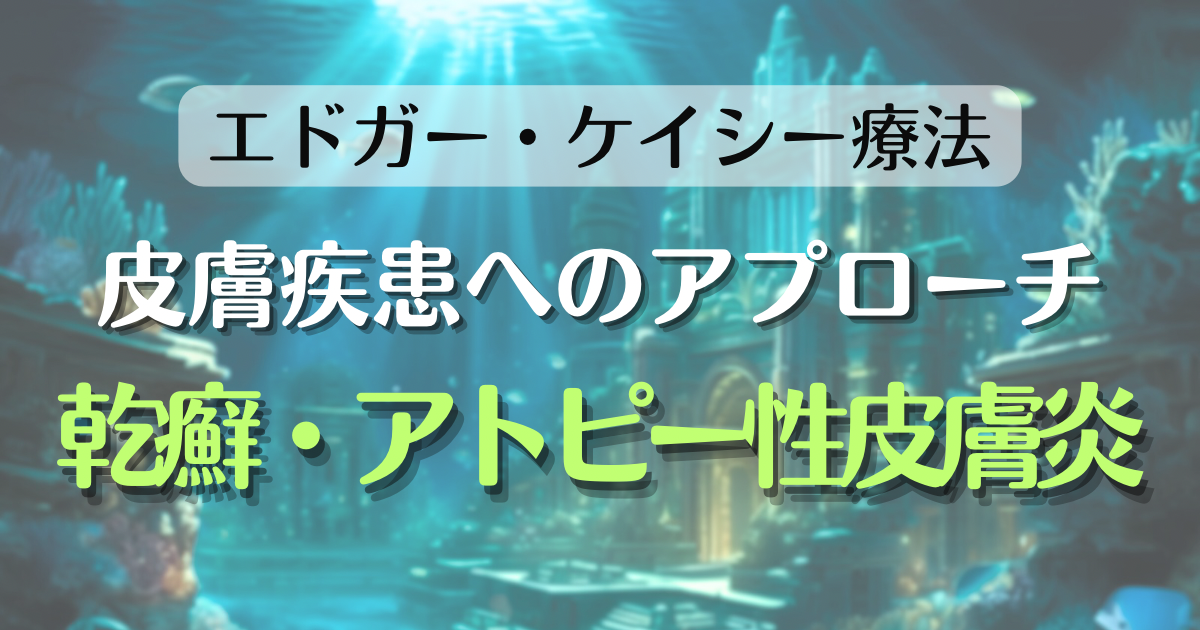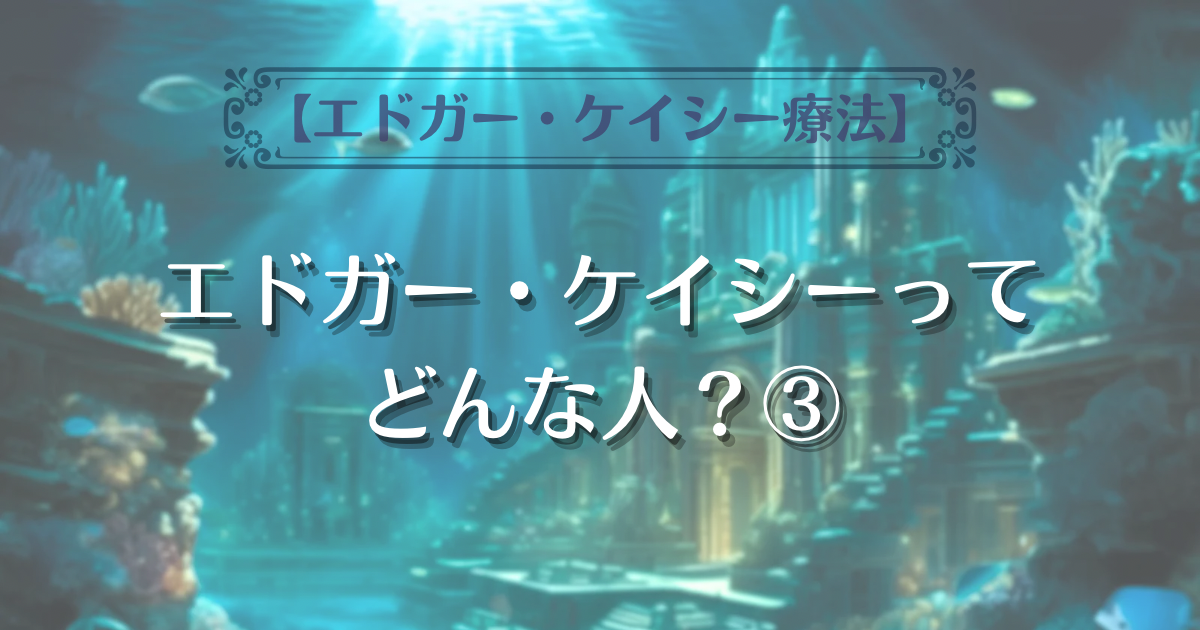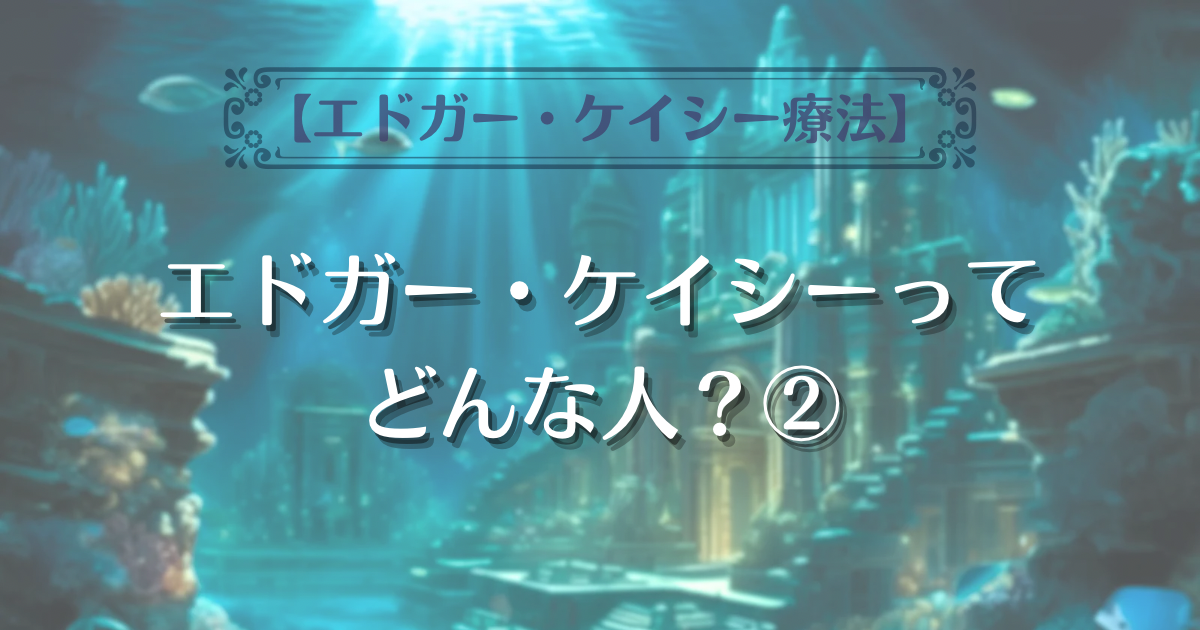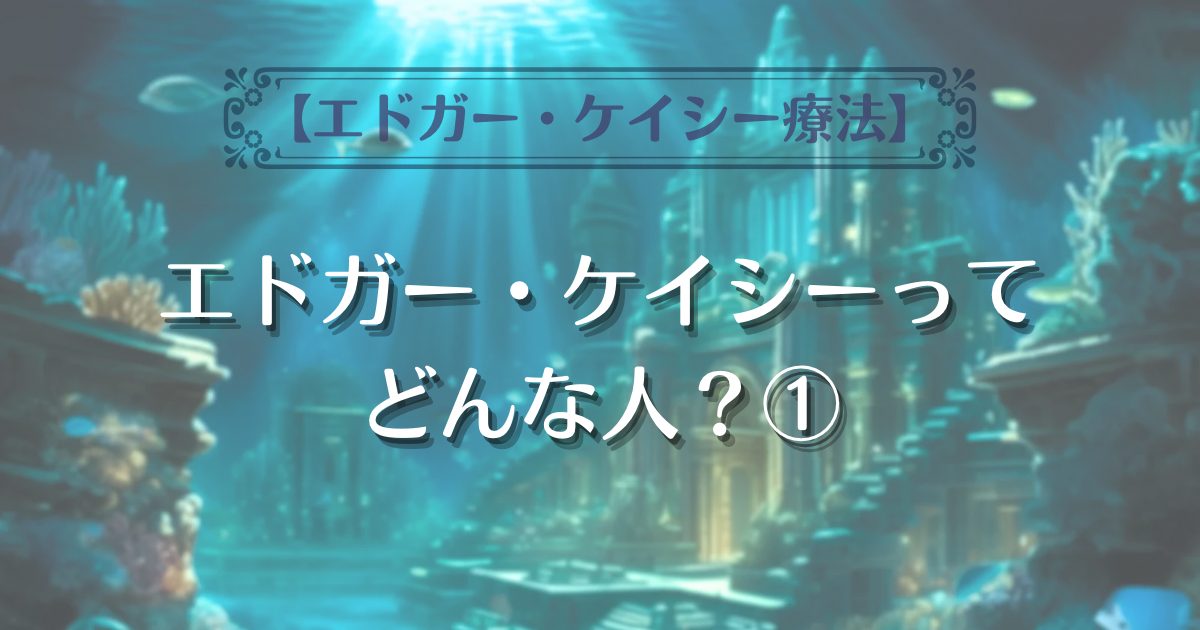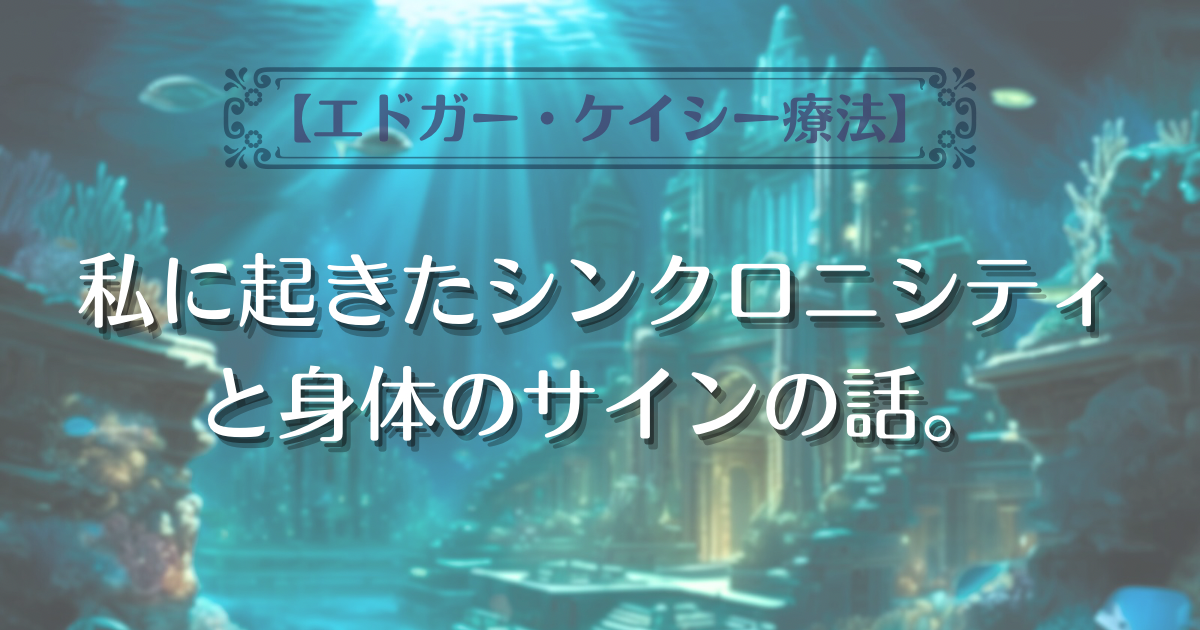はじめに
今回は、エドガー・ケイシーが推奨した、具体的な食事療法の基本についてご紹介します。
ケイシー療法では様々なアプローチがありますが、そのすべてのベースとなるのが「食事療法」です。ここをおろそかにすると、他のケアの効果も出にくいと考えられているため、非常に大切にされています。
ケイシーのリーディングでは、体の不調の多くは、消化・吸収・排泄といった体の基本的な働きが滞っていることから来ると考えられています。

食事は、体が栄養を取り込み、エネルギーを生み出すための「燃料」です。その燃料が体に合っていなかったり、うまく消化・吸収・排泄できなかったりすれば、当然、体は本来の機能を発揮できません。
ケイシー療法が提唱する食事ルールは多岐にわたりますが、まずは特に重要とされる基本の10原則を押さえることから始めましょう!
エドガー・ケイシーが勧めた食事療法の基本10か条

1. 豚肉を避ける(No Pork)
これはケイシーが非常に強調した点の一つです。豚肉はほとんど禁食とされています。特に、これから健康を回復しようとする人は、徹底して豚肉を避けることが推奨されます。
なぜ豚肉が避けられるのか、ケイシー自身は明確な理由を示していませんが、ケイシー療法の研究家の間では豚肉の脂の溶ける温度に関係があるのではと考えられています。
例外として、徹底的に脂を抜く調理法(例:沖縄のチビチのように長時間煮込んで脂を除く)であれば少量許容されることがあります。また、脂のない部位(例:レバー)は食べても大丈夫とされています。
どうしても四つ足の肉を食べたい場合は、牛肉はときどきなら良く、ラム肉(子羊)が最も推奨されています。ラーメン店の豚の脂たっぷりなスープなどは、ケイシーの考えでは「病気まっしぐら」な食べ物とされています。
2. 揚げ物を避ける(No Fried Food)
豚肉と並んで、非常に高い頻度で避けられるべきとされるのが揚げ物です。加熱されて酸化した油が体にとって大きな負担となると考えられています。換気扇に付くようなベタベタした油が、体内に取り込まれるイメージです。
どうしても揚げ物を食べたい場合は、ゴマ油で揚げることが例外的に許容されることがあります。ゴマ油は加熱によって安定性が増すと考えられているためです。しかし、健康回復を目指す上では、そもそも揚げ物を避けるのが賢明です。
3. 新鮮な野菜を豊富に食べる
新鮮な野菜は体に良いと広く知られていますが、ケイシー療法ではその種類と食べるタイミング、比率にもこだわりがあります。
地上で育つ野菜 & 地下で育つ野菜
地上で葉を茂らせる野菜(葉物など)を全体の2~3の割合にし、地下に育つ根菜類を1の割合にするのが理想です。地上に伸びる野菜には「立ち上がる」気力があるとされ、活動的な昼間に適しています。
食べるタイミング
葉物野菜は、酵素を壊さないようできるだけ生で、ランチに食べるのが理想です。地下の野菜は、夜に温野菜にして食べるのが良いとされます。
推奨される野菜
特にクレソン、セロリ、レタス、ニンジンの4つが推奨されていますが、その他にも、基本的に「緑の濃い新鮮な葉物野菜」は推奨されます。日本野菜では、チンゲンサイ、ミズナ、ホウレンソウ、シュンギクなども良いと考えられています。(※ただし、ホウレンソウはシュウ酸の量が若干多いため、石のできやすい方は生よりも一度湯通しすることが推奨される場合があります。)
また、葉物野菜以外の中では、ニンジンが非常に重要であり、血液の凝固力を高める点が最も重要視されています。これは、免疫細胞が病原菌を攻撃する際の材料になると考えられており、がん予防にも繋がるとされています。さらに、ニンジンは目にとても良いとされ、特に葉っぱのつけ根が良いと言われています。
ドレッシング
オリーブオイルにレモン汁、少量の塩コショウで味付けしたものだとベストですが、マヨネーズやポン酢、シーザードレッシングなどでもOK!味付けは自分が美味しく食べられるよう好きにアレンジして構いません。
【重要】皮膚疾患のある人はナス科の野菜を避ける
アトピー、湿疹、乾癬などの皮膚疾患がある場合、ナス科の野菜は避けるべきと強く勧められています。ナス科の植物には、もともと有毒なものが多く含まれており、それが皮膚を荒らす食物毒素となるためです。
具体的に避けるべきナス科の野菜は以下の通りです。
- ナス
- トマト
- ジャガイモ
- パプリカ
- ピーマン
- トウガラシ
- コショウ(香辛料)
これらは健康な人にとっては問題ない場合が多いですが、皮膚が弱い人には影響が出やすいとされています。調理法で毒性が軽減されることはないため、皮膚のトラブルがある場合は徹底して避けることが重要です。実際に、長年の湿疹がトマトジュースをやめただけで改善した症例も存在します。
4. 野菜を食べる際はゼラチンを一緒に摂る
これはケイシー療法独特のアドバイスです。ときどきで良いので、野菜と一緒に(あるいは同時に食事の中で)、ゼラチンを摂ることが推奨されます。
理由は、体内にゼラチン質があることで、ビタミンの吸収率が約7倍に増大するとケイシーは主張したためです。特に分泌腺に良い効果があるビタミン吸収を高める目的です。
寒天は植物性ですが、ゼラチンは消化しやすい動物性たんぱく質なので、必ずゼラチン表記のあるものを選びます。ゼリーとして食べたり、パウダーを溶かしたり、サラダにかけたりするなど、摂り方は自由です。週に数回摂るだけでも良いとされています。
5. 精白した米、パンは避ける
白米や精製された白いパンは、栄養価の面から避けることが勧められます。代わりに、玄米や分づき米、全粒粉パンやライ麦パンなどを選ぶのが良いでしょう。
玄米に慣れていない場合は、消化の負担を減らすために、まずは五分づき米などから試してみるのが良いとされています。
6. 1回の食事で複数の穀物を同時に食べない
これはケイシー療法の中でも特に特徴的なルールの一つです。同じ食事の中で、種類が異なる穀物(炭水化物)を組み合わせて食べないようにします。
例えば、「ご飯とラーメン」「ご飯とうどん」「パンとパスタ」といった組み合わせは避けるべきです。また、ジャガイモは穀物として扱われるため、「ご飯とジャガイモが入ったカレー」なども避けた方が良いとされます。
理由は、異なる種類の穀物はそれぞれ消化に必要な酵素や条件が微妙に違うため、同時に食べると未消化物が生じやすくなるためです。未消化物は腸内で腐敗菌を増やす原因になると考えられています。
同じ玄米を使ったパンと餅でも、加工法が違えば消化時間も変わるため、同時に食べるのは避けるべきとされています。消化力が非常に弱っている場合には、1日を通して1種類の穀物だけにするという、さらに厳しい制限が推奨されることもあります。通常は「1回の食事で1種類」を守るようにします。
7. 柑橘系の果物を豊富に食べる
ミカン、レモン、ライムなどの柑橘類は積極的に食べることが推奨されます。これらは体を弱アルカリ性に保つのに非常に有効だからです。現代人の体は酸性に傾きがちですが、柑橘系はこれを素早くアルカリ化する働きがあると考えられています。
【重要】柑橘系は炭水化物と一緒に食べない
ただし、柑橘系の果物を炭水化物(穀物)と一緒に食べることは絶対に避けるべきとされています。食後にすぐミカンを食べたり、パンと一緒にオレンジジュースを飲んだりするのはNGです。
柑橘系は単体では体をアルカリ化しますが、炭水化物と一緒になると強い酸性として働くと言われています。食べる場合は、炭水化物の食事から前後2時間ほど空けるのが望ましいです。食間のおやつとして食べるのが良いでしょう。
体を急速にアルカリ化したい特別な方法として、朝食にミカンだけを食べる日を設けることが勧められています。毎日ではなく、通常の朝食と交互に行う(例:月水金はミカン、火木土はご飯)のが最も効果的とされます。体が弱アルカリの状態では、インフルエンザウイルスが増殖しにくいという考えに基づいています。
なお、市販の濃縮還元ジュースではなく、新鮮な果物をそのまま、あるいは絞って飲むのが良いとされています。
その他の果物もほとんどは推奨されますが、生のリンゴとバナナは注意が必要です。生のリンゴは特定のダイエット時以外は避け、口内炎やヘルペスの人はいかなるリンゴも禁食です。バナナは未成熟な輸送されたものでなく、調理(加熱)したものだけが良いとされます。
8. 1日1.5リットルの水を飲む
健康維持のためには、1日にコップ7〜8杯、合計1.5リットル程度の水を飲むことが推奨されます。これは日本の体格に合わせて調整された量です(米国人向けは2リットル)。腎臓が老廃物を適切にろ過するためにも、十分な水分が必要と医学的にも言われています。
ここでいう「水」は、あくまで普通の水です。コーヒーや紅茶、アルコールはカウントしません。むしろアルコールは利尿作用があり、さらに水分が必要になります。薄いハーブティー程度なら含めても良いかもしれません。
意識しないと達成しにくい量なので、常に手元に水を置いてこまめに飲むようにすることが勧められています。生水か湯冷まし(白湯)かは、その土地の水の質や個人の体質で判断しますが、不安なら湯冷ましの方が安全で健康的とされます。まとめて作って保存するのも良い方法です。
コーヒー・紅茶にミルクは入れない
コーヒーや紅茶を飲む際は、できるだけミルクを入れないようにアドバイスされています。ミルクを入れると胃粘膜を荒らす可能性があるためです。
9. 砂糖を多く含む菓子類を食べない
精製された砂糖が多く使われている菓子類(ケーキなど)は避けるべきです。多くの人が抵抗を感じる項目ですが、体を健康な状態に整えていけば、自然と甘すぎるものを欲しなくなることが多いとされています。
どうしても甘いものが欲しい場合は、蜂蜜やメープルシロップといった、精製されていない自然な甘味料を選ぶことが推奨されます。精製度の低い黒砂糖なども少量なら良いとされますが、蜂蜜やメープルシロップがより望ましいです。
10. 怒っているとき、悲しんでいるときには食べない
感情が激しく揺れ動いている時には食事をしない、というのもケイシー療法の特徴的なルールです。怒りや悲しみといった強い感情は、消化系の働きを阻害してしまうためです。
感情が波立っているときに口にして良いのは、水だけとされています。心が落ち着いてから食事をするようにしましょう。
まとめ
エドガー・ケイシーが推奨する食事療法は、単に「何を食べるか」だけでなく、「どう食べるか」「いつ食べるか」「何と組み合わせて食べるか」といった、より実践的で体への負担を減らすための知恵が詰まっています。
今回ご紹介した10の原則は、
- 避けるべきもの(豚肉、揚げ物、精製された砂糖や穀物、特定の野菜/果物、ミルク入りの飲み物、感情的な状態での食事)
- 積極的に摂るべきもの(新鮮な野菜、柑橘類、水)
- 摂り方の工夫(野菜の比率・タイミング、ゼラチン、穀物の組み合わせ、柑橘類を摂る時間)
といった幅広い視点から、体の消化・吸収・排泄のプロセスをスムーズにし、体のアルカリ度を保つことを目指しています。
これらの原則全てを一度に完璧にこなすのは難しいかもしれませんが、まずはご自身の生活に取り入れられそうなものから、少しずつ始めてみましょう!
参考文献:エドガー・ケイシー療法のすべて(1)